不動産売買に伴う主なトラブル5つ
本コラムでは、不動産の売買トラブルについて5つの事例を挙げながら、弁護士がお役に立てる場面や相談するメリットについて…[続きを読む]
東京弁護士会所属、千代田区の弁護士事務所。法律相談を承ります。

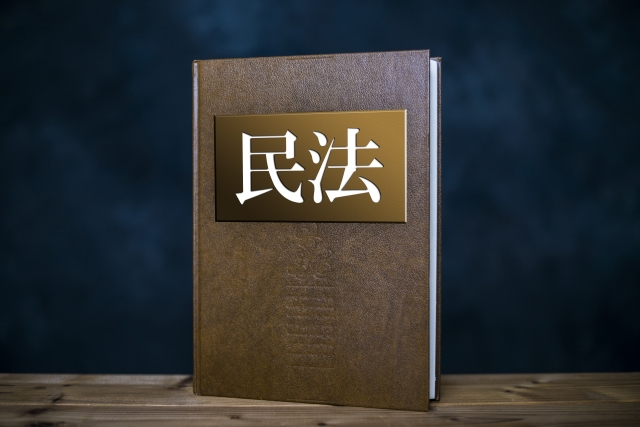
このコラムでは、
などについてご説明いたします。
契約不適合責任に限定しない不動産売買のトラブルについては、以下のコラムをご覧ください。
目次
従来、売買の目的物に欠陥があることを「瑕疵」という表現をしていました。
しかし、「瑕疵」という表現は一般の人に分かりづらい表現であったこと、以前から「瑕疵」が契約当事者の合意や契約の趣旨に照らして、通常の品質や性能を欠くことを意味していたことから、「瑕疵」の用語を改め、判例・通説上の「瑕疵=目的物が契約に適合していないこと」という考え方を法律上も明文化したものです。
瑕疵担保責任は、「隠れた瑕疵」に限定されていました。
「隠れた」という要件が必要とされたのは、買主が瑕疵の存在について知っていた場合、また、買主が注意すればわかったであろう場合には、必ずしも買主を救済する必要がないと思われることから、「隠れた瑕疵」に限定されていたのです。
しかし、契約に不適合な品質や性質の物であれば、外形上明白な欠陥があっても修理や追完を認めた方が適切な場合もあり得ます。
そのため、契約不適合責任には「隠れた」という要件は不要になり、民法改正後は、買主が契約不適合であることを知っていたとしても、また、知らなかったことに買主の不注意があったとしても、買主は契約不適合責任のルールによって救済されることが明文化されました。
従来の民法では、買主は売主に対し契約を解除し損害賠償請求をする方法が規定されているのみでした。
また指定した数量が不足していた場合や物の一部が滅失していた(なくなっていた)場合等に代金減額請求が定められていました。
しかし、欠陥品を納入した場合の売主が、欠陥のない目的物を納入し履行を追完することは、契約上当然のことであり、実務でも履行の追完は一般的に行われており、履行の追完を定める契約書も多くありました。
そのため改正民法では、「損害賠償の請求」や「契約の解除」に加えて、新たに「履行の追完の請求」が明文上も定められ、履行の追完がなされないときや履行の追完ができないときに、契約不適合の程度に応じて「代金の減額の請求」をできることが記されました。
具体的な内容については後述します。
契約不適合とは、引き渡された目的物が、当事者の合意や契約の趣旨に照らして、通常又は特別予定されていた種類・品質・数量を欠いており、契約の内容に適合しないことをいいます(民法562条1項)。
なお、契約上予定されている目的物の種類・品質・数量は、契約書の文言やその趣旨のほか、通常有するべき品質等に照らして決められることになります。
改正民法では、救済方法として以下の4つが明記されました(民法562条、563条、564条)。
なお、③の損害賠償の請求や④の契約の解除は他の救済手段と併用することが可能です。
売買の目的物の種類、品質または数量に関して契約不適合がある場合に、買主は売主に対し、目的物の修補請求権や代替物・不足物の引渡請求をすることができます。
例えば、目的物に欠陥があった場合に、その物を欠陥のない物と交換させる、数量が不足していた場合には不足分の数量を改めて納品させる等が請求できることになります。
買主が売主に相当期間を定めて履行の追完を催告したが、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額請求ができます。
つまり、買主から履行の追完をしてもらえないときに代金の減額請求ができることになります。
例えば、売買の目的物が10個だった場合に8個しか納品されず、不足分の2個の追完請求をしても追完がなされない場合に不足分2個分の代金を減額請求できることになります。
なお、履行の追完ができない場合等には催告をしても意味がありませんので、その場合には直ちに代金減額の請求ができることになっています。
目的物が欠陥品であったことにより、買主が損害を被った場合、買主は損害賠償を請求できるというものです(債務不履行に基づく損害賠償請求といいます)。
目的物の欠陥によって生じた実損害や、目的物の転売を予定し購入したが、転売する機会を失ったことによる転売利益を請求する等が考えられます。
ただし、損害賠償請求は、目的物に契約不適合があれば直ちに認められるものではありません。
損害賠償請求をするためには、売主の責めに帰する事由により目的物が契約不適合になったことが必要であり、その点で履行の追完請求・代金減額請求・契約解除と異なります。
売買の目的物に軽微ではない欠陥があった場合、買主は原則として売主に相当期間を定めて、契約の履行を催告し、相当期間内に履行がないときに、買主が契約を解除することができます(債務不履行解除といいます)。
その場合は、目的物を返品する必要があります。
なお、契約解除ができるのは、目的物に契約不適合がありさえすれば認められるものではありません。
当該契約や取引上の社会通念に照らして軽微であるときは契約解除ができませんので、注意が必要です。
売主が契約に適合しない目的物を買主に引渡した場合に、買主はその不適合を知った時から1年以内に売主に通知しないと、その不適合を理由として、履行の追完請求、代金の減額請求、損害賠償の請求、および契約の解除をすることができません。
ただし、売主が目的物を引き渡した時にその不適合を知り、または重大な不注意によって知らなかったときは(悪意・重過失といいます)、買主の救済期間を上記期間に限定する必要性はないことから、その期間を経過しても買主は売主に対して契約不適合責任を追及できることになります(民法566条)。
なお、買主の契約不適合責任に基づく請求には時効があり、追完請求等を行使できることを知ったときから5年間(追完請求等を行使できることを知らない場合は10年間)で時効消滅しますので、注意が必要です。
契約書で売主は契約不適合責任を負わない旨規定しておけば、売主は契約不適合責任を負わないのが原則です。ただし、以下の例外があります。
宅建業者が売主となる宅地又は建物の売買契約では、契約不適合責任を負わないとの特約は無効となります。
ただし、売主と買主との間で、契約不適合責任の期間を目的物の引渡しから2年以上とする特約をする場合は除きます(宅建業法40条1項、2項)。
事業者と消費者の間の売買契約では、損害賠償の責任の全部を免除する条項は無効となります(消費者契約法8条1項1号)。
さらに、事業者が債務を履行しないことにより消費者に損害が発生した場合において、事業者が意図的に債務を履行せず、また通常は払うべき注意すらも怠って債務を履行しない場合(故意・重過失がある場合)の損害については、その責任の一部を免除する条項も無効となります(同項2号)。
契約不適合責任は、引き渡された目的物が、当事者の合意や契約の趣旨に照らして、通常又は特別予定されていた種類・品質・数量を欠いている状態のことをいいます。
ですから、契約不適合の有無について売主と買主間で争いが生じないように、どのような目的物が契約上予定されているかを契約書で明確に規定しておいた方がベターです。
契約不適合責任は、引き渡された目的物が当事者の合意や契約の趣旨に照らして、その種類・品質・数量が契約に適合しない場合には、契約不適合の存在を買主が知っていたかどうかにかかわらず、売主は契約不適合責任を負うことになります。
また、売主が目的物の引き渡しの時にその不適合を知り、または重大な不注意によって知らなかったときは、買主はその不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなかったとしても、売主は契約不適合責任を負うことになります。
ですから、売主は、引渡し前に目的物が契約不適合ではないか否か、入念にチェックすることが大切です。
前述のとおり目的物が契約不適合であった場合、買主の救済手段は4種類あります。
買主としてはまずは欠陥品の修理や代替品を求めて追完請求をすることになりますが、同時に損害賠償請求を行い、軽微な欠陥でない場合は契約の解除もできます。
従いまして、買主は状況に適した救済手段を選択すべきですが、どの契約不適合責任で請求するべきであるかは、法律の知識が必要となりますので、弁護士に相談した方がベターかと存じます。
改正民法が2020年4月1日に施行されていますので、契約締結が改正民法の施行日(2020年4月1日)より前の場合は瑕疵担保責任、施行日以降の場合は契約不適合責任が適用されます。
個人(事業者である場合を除く)が売主の場合には、任意に契約不適合責任を免責する特約を定めることができるため、買主さえ合意すれば、原則としては、売買の対象となる不動産に契約不適合があったとしても、免責されることになります。
そのため、売主側は、トラブルを防止するためにも、可能な限り、不動産の状態や状況を詳細に把握し契約書や重要事項説明書等に記載した方がいいと思われます。
免責特約がある場合、買主は原則としては契約不適合責任を問えない可能性もあることから、できるだけ契約前に専門家によるインスペクション(建物調査等)をお願いし、不動産の状況を確認をしておくとよいでしょう。
契約不適合責任はあくまで売主が負うべき責任であり、不動産仲介業者はこの責任を負いません。
しかし、仲介業者は、不動産売買契約の履行により、契約当事者双方が契約の目的を達成できるよう業務を執り行う義務を負っています。そのため、売買目的物に関連する事項についての調査・説明を行うなどの責任を負うことになります。
民法改正により、瑕疵担保責任が契約不適合責任という表現になり、買主の救済手段が明文化されわかりやすく整理されました。
しかし、どのような場合に契約不適合責任が請求できるのか、どの救済手段を用いることができるのか、具体的どのように売主に請求したらよいのかについて、高度な法律的な判断が必要であることは、改正前後で変わりはありません。
不動産売買で不動産に契約不適合の問題があった場合は、まず弁護士に相談することをお薦めいたします。
あたらし法律事務所は不動産トラブルの経験が豊富で、様々な問題を解決してきましたので、是非ご相談ください。

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-30
紀尾井町山本ビル5F
東京メトロ「麴町」駅1番出口より徒歩約5分
東京メトロ「永田町」駅5番・9番・7番出口より徒歩約5分
東京メトロ「赤坂見附」駅D番出口より徒歩約8分
東京メトロ「半蔵門」駅1番出口より徒歩約8分
JR「四ツ谷」駅麹町口より徒歩約14分